- 息子 療育園→小学校支援級→普
通級+通級 現在小学生。 - みお パート主婦。おでかけ好き。
- 旦那 息子に勉強を教えてくれる。
- ハムスター 臆病な性格の1歳。
筆者の自己紹介です。
小学校・特別支援学級の見学に行ってみた感想
息子が年長になる5月ごろから本格的に小学校の見学に行き始めました。全クラスを自由に見学することができる期間「学校公開」の時の支援級を見に行きました。息子が年中の時からちょくちょく行っていました。
うちの地域では、支援学級は定員が決まっています。定員は年によって違うのですが(六年生の卒業で抜ける人数による)、1人でも定員オーバーしたら抽選です。
全ての小学校に支援級が入っているわけではないので、徒歩で無理なく行けるのは1校のみでした。
他の小学校は自転車やバス、電車を使わないと辛いです。毎日行き、帰りと送らないといけないので、結構きついですね。
後からわかったのですが、バス代や電車代の補助はうちの地域の場合は後から出るようでした。
よくブログなどで、「普通級と支援級を行ったり来たりできる」というのを読んだことがあるのですが、うちの地域の場合は、「支援級に入ったら普通級の授業を受けられることはほとんど無い」です。
先生が「大丈夫そう」と判断した子については、1科目だけ普通級の授業を受けることが出来るようですが、、
あとはクラスのみんなで受けに行くことがごく稀にある程度。 遠足や持久走、運動会などは普通級の各学年に入って一緒に参加しますが、
ほとんどは支援級の中で毎日を過ごすことになります。休み時間も、普通級は教室、体育館、校庭などへ行けますが、支援級は先生が一緒で、プレイルームと呼ばれるお部屋か、校庭とかは少し違う外の空間で遊びます。
5校見に行き、ゆくゆくは普通級で授業を受けることも出来るか?等質問しましたが、どこも同じような回答でした。
これについては本当に地域によるのですが。
大抵、支援級は、昇降口を入ったら、普通級とは全く別の・・職員室の近くなどにポツンとあることが多かったです。
生徒8人に対して先生1人という割り当てで、うちの学校に関しては、先生4人に対し、生徒28人くらいという感じでした。
1年生から6年生まで各1~5名くらい居ましたね。
他の学校では、人数の少ない学校、支援級全員合わせて10名ほど。という学校もありました。
自由でのびのびした校風で少しくらいやんちゃでも放任、寛容?な学校、
ピシッと先生の言うことを聞いて、立ち歩く子はひとりも居ない学校。支援学級も、色々特色が違いました。
うちの方では「情緒」という支援級が無いので、「知的」の支援級になります。
登下校は毎日教室まで親が送り迎え、もしくは帰りは「放課後等デイサービス」を使っている方が多かったです。
もう一度就学相談を受け直して、「普通級で良さそう」という判定が出れば、支援級に入った後でも、普通級へ移ることはできます。かなり少ない事例だとは聞きました。
放課後等デイサービスとは?
受給者証を使用して、学校まで迎えに来てもらい、帰りは自宅まで送ってくれる、学童のような施設です。
子どもの発達を促すようなプログラムがあったり、皆で遊んだり、宿題をしたりして過ごします。
こちらの記事で触れています。(こちらでは未就学児が利用できる施設についてですが、基本的にはさほど変わりません)
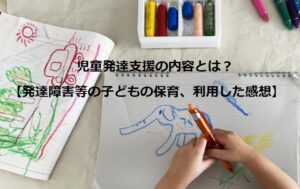
特別支援学級、特別支援支援学校に入る基準
特別支援学級の場合
発達上の判定が軽度域の子どもが対象。(おおよそIQ50~75)地域の定められた学校内に併設されている。身辺処理はほぼ自立している。
オムツは外れていることが条件でした。

特別支援学校の場合
発達上の判定が中~重度域の子どもが対象。(おおよそIQ50以下)特定の学校となる。登下校は送迎バスによる。下校はデイサービスを使っている方も多い。
クラス編成は単一障がい学級と、重度重複障がい学級の二つに分かれていることが多い。
身辺自立等が困難なお子さんもいる。1クラス3人程度、学校による。
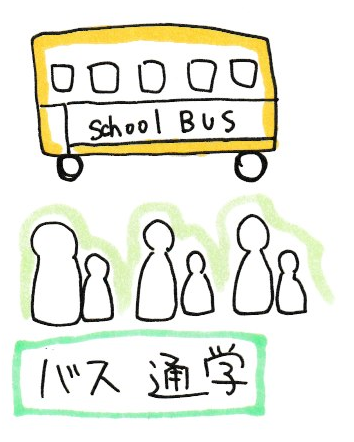
 みお
みお特別支援学校へ見学に行ったことがありますが、校門に暗証番号付きのカギが付いていました。
自閉症学級などもありました。
通常学級
IQおおよそ75以上。30名前後に対して担任1名。
通級(コミュニケーション等に困難がある子供対象)を利用することもできる。
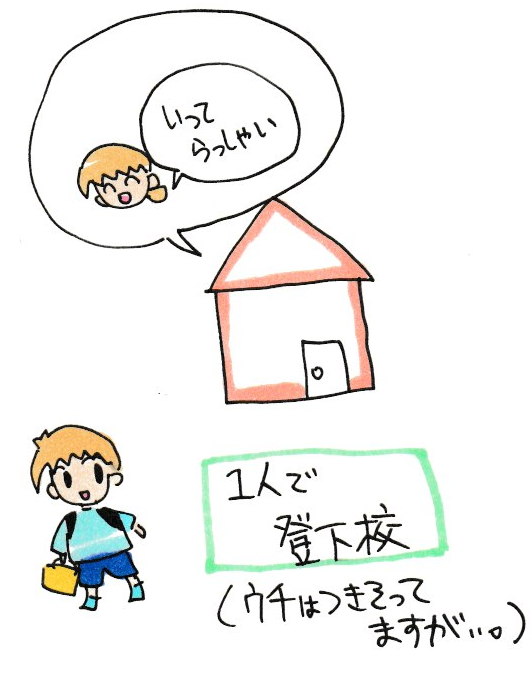
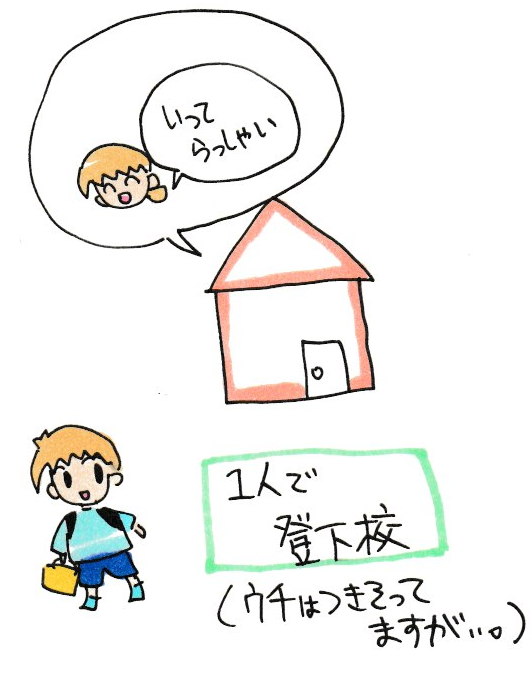
特別支援学級で1年生を過ごしてみました
第一希望の近い小学校に、運よくこの年は希望者が少なかったので、抽選もなく入学することが出来ました!
入学式、普通級のクラスの後ろの方の席で、参加しました。支援級の先生が一人、側についていてくれたので心強かったです。
息子もきちんと座って事なきを得ました^^
コロナなので来賓の話などなく、短時間で終わるのは、親子ともども助かります。
集合写真は普通級のクラスに混じって参加しました。
入学前に一度、体験授業はあったのですが、本格的にはこの日から学校生活が始まるので、どうなるのかな?という不安がありました。
休み時間の過ごし方は、先生に連れられて校庭へ行き、「転がしドッジボール」という遊びをよくしていたようです。
プレイルームでは各自好きなことをしたり、みんなでダンスを踊ったり。
運動会につては、「連合運動会」という地域の他の学校(支援級のみ)が集まって行う運動会というものもありました。
なので、自分の小学校の運動会(普通級と一緒に)と、連合運動会の2回参加する感じになりますね。
それから、
担任の先生と毎日やり取りをする、「連絡帳」がありました。翌日の時間割、持ってくるものなども書かれています。
子どもの様子も保育園の連絡帳のような感じで毎日書いてくれます。聞きたいことも、連絡帳を通して聞くことができます。
息子は、先生に厳しく「あれしてこれして」と指示を受けるのが嫌だったのか、慣れない環境のせいなのか、
結構ぎゃーぎゃーそしていたようで、毎回「ダメな部分」を連絡帳に書かれていて私も参ってしまいました・・・。
この時通ったいた放課後デイサービスでは荒れに荒れて、「うちでは面倒見れないかも」を思われていたこともあったと後に聞いてびっくりでした‥‥。
個人面談でもボロボロに色々言われる始末…。
授業は低学年、高学年に分かれて行われておりました。教科書やノートを使ったり、黒板を書き写したりすることは無く、用意されたプリントをやっていく感じです。
一応個人のレベルに合わせてあるようです。
教科書はもらっただけで一度も使いませんでした。
宿題は一応プリントがありました。
夏休みの宿題なども、プリントが主です。書初めなどは高学年にならないとやらないようでした。
登下校の旗持ち当番は子供の送迎があるので免除、役員も低学年のうちは無しでした。
少し残念でしたのが、植物を育てたり・・が支援級には無かったこと。ヒヤシンスとかチューリップ、あさがおを育てるなどの。クラス全体でひとつ?育てて居るようでしたが。
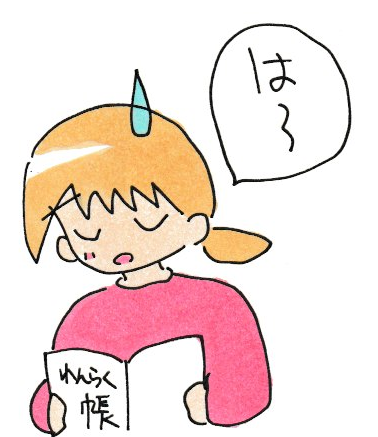
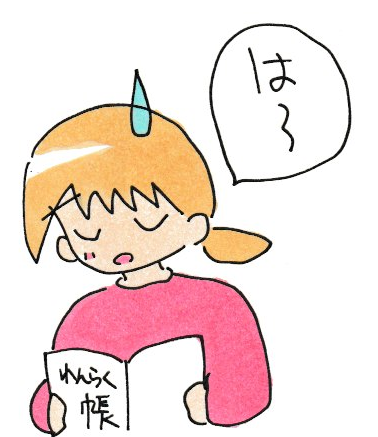
まとめ
特別支援学級のメリットは、「勉強は個人のレベルに合わせてもらえる。」、「登下校は親が付き添い(高学年になったり、大丈夫そうだと判断された場合は自力通学できる)、
休み時間も先生の目が届いていて安心」というところでしょうか。
連絡帳で学校での様子もわかりやすいです。
とにかく安心!という感じですね。
デメリットは、一度特別支援学級へ入ってしまうと、勉強の進め方が全く違うので、普通級へはなかなか戻れないこと←説明会の時に先生に言われました。
戻る場合は低学年までに。との事でした。
学校によっては、普通級との交流はほとんど無いこと。
でしょうか。お子さんそれぞれに合った進路を見つけていけたらよいなと思います。
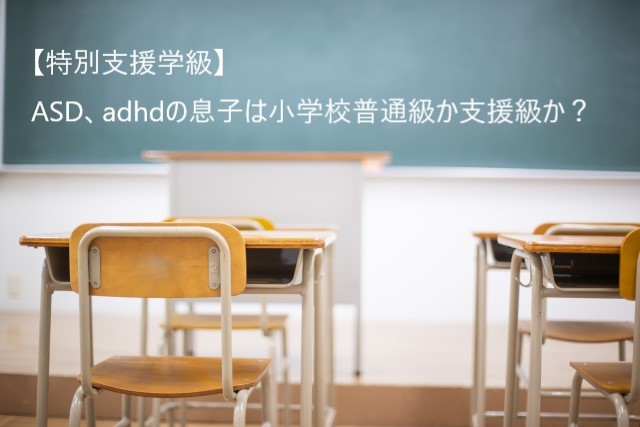

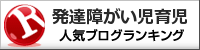

コメント